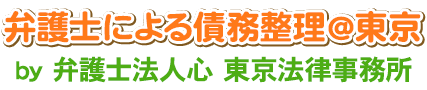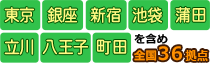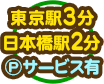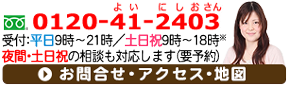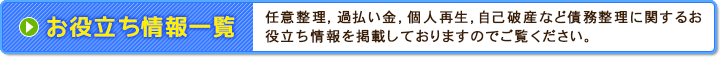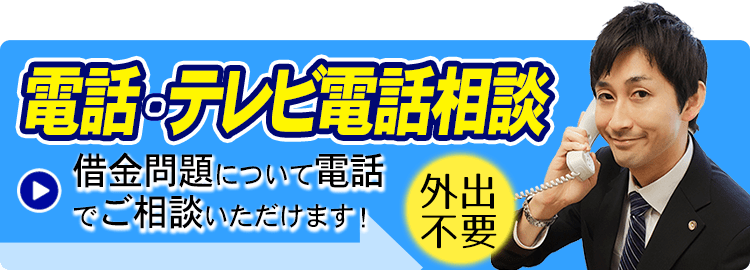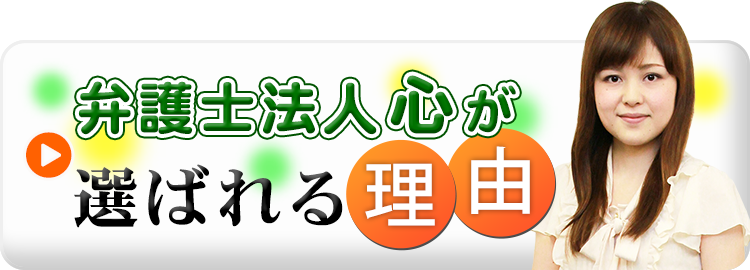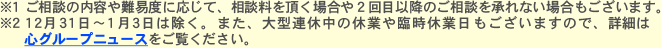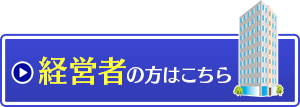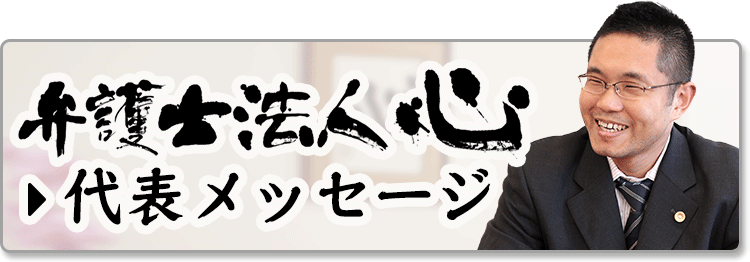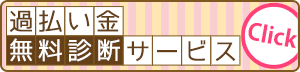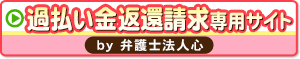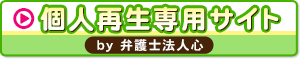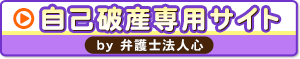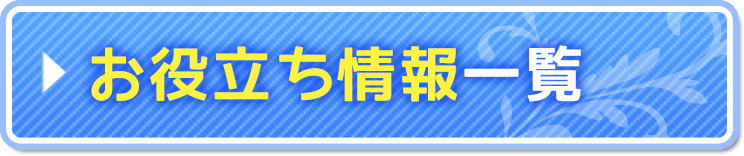「時効の援用」に関するQ&A
時効援用をするリスクにはどのようなものがありますか?
1 時効援用はいつ行うべきか
時効の援用をどのタイミングで行うべきかは、意外と難しい問題です。
時効の援用ができる状態になっているなら速やかに行うべき、という考え方もあると思いますが、そもそも時効の援用ができる状態になっているかどうかの判断が簡単ではありません。
時効の援用ができると思って手続きをしたら、時効が成立しなかった、ということもありますので、ここでは時効援用についてのリスクをお話しいたします。
2 裁判を起こされているケース
上述の通り、時効が成立すると思って手続きをしたけれども時効が成立しなかった、ということがあり得ます。
最終取引から5年が経過することで時効になるというのが一般的な考え方ですが、その間に裁判を起こされている場合には、裁判の判決から10年経過しないと時効にはなりません。
裁判を起こされた覚えがないという場合でも、引っ越しをしていて以前の住所に裁判所の書類が届いていたため気づけなかったということもありますし、また、自宅を留守にしていて裁判所からの書類を受領できず、不在票にも気づけなかったということも少なくありません。
信用情報を確認したとしても、裁判を起こされているかどうかは記載されていないため、実際に時効の援用をしてみないとわからない、つまり手続前に時効が成立するか否かを確実に判断することは困難ということになります。
3 最終取引日が不明確な場合
最終取引がいつだったのか自体が不明確な場合も、時効期間が経過していない可能性がある以上、時効が成立しないリスクがあります。
また、細かい話になってきますが、最終取引から5年経っていても一括請求されてから5年経っていないという場合、一部しか時効にならないということもあります。
4 リスクを抑えるための方法
時効の援用は後になって行うほど、時効期間が経過する可能性が上がりますので、失敗のリスクが下がるといえます。
ただし、上述の通り裁判を起こされて判決が確定してしまうと、そこから10年経たないと時効が成立しないことになってしまいますので、裁判所から書類が届いたタイミングで時効の援用手続を行うのが最も失敗のリスクが下がるタイミングといえます。